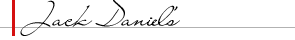 | Bourbon Street | Wild Turky | Bombey Sappire | Dimple |
| Bourbon Street | Wild Turky | Bombey Sappire | Dimple |
 深夜のバーカウンターでバーボンを飲み始めると、自分の時間がやってくる。
深夜のバーカウンターでバーボンを飲み始めると、自分の時間がやってくる。
自分の時間というものは、ひっそりと足音も立てずにやってきて、ふと気付くとカウンターの隅に座っていたりする。
当然、時間というものには実態がないけれど、空気の密度が変わったり、光の角度が微妙に変わるのでわかるのだ。時間という物の質感は酔っ払っていないと体感できない。
自分の中に存在するある種の規律を放棄したときに、通常の生活の中で封印されていた鋭敏な感覚が働きはじめるからだ。
バーボンを飲み始めると、ありきたりな日常を放棄することにためらいがなくなる。
欧米では、こんな時にピンクの象が見えると言うけれど、今の私の視界に写っているのはジャック・ダニエルズの入ったロックグラスだけだ。
私はこのバーでの払いをCash on Deliveryにしているので、カウンターの上には何枚かの札と硬貨が残っている。淡い照明の下で、Cashはひっそりと陰を作っている。
そして、カウンターで時間を過ごすうちに睡魔がやってきて、いつもと同じように夜が更けてゆくのだろう・・・
ふと気付くと、カウンターに突っ伏した私の右腕にカシミアのセーターを捲り上げた白い腕が絡まっている。
カウンターの中では髪をアップにしたユミコが私たちを睨みつけていた。
 「おい、いったい俺が寝ている間に何が起こった?」私は突っ伏したままの状態でユミコに囁いた。
「おい、いったい俺が寝ている間に何が起こった?」私は突っ伏したままの状態でユミコに囁いた。
「そりゃ私が聞きたいわよ。」彼女の怒りは爆発寸前だ。
私は寝ているわけにはいかず、ゆっくり体を起こした。もちろん私の右隣の女性の腕をゆっくり解きながらだ。
「目が覚めたらこんな状況になっていたけど、俺何か悪い事したのか?」
「貴方がカウンターで寝ていると、彼女がフラフラしながら入ってきて隣に座ったの」
「そして、貴方の名前を呼んで、腕を絡めて寝ちゃったのよ」
「いったい誰なんだ?これじゃあ顔も確認できないぜ」
私の隣で見知らぬ女性は突っ伏したまま寝息を立てている。その時、謎の女性が姿勢を変えたので、寝顔がチラっと見えた。
懐かしくも腹立たしい顔がスヤスヤ寝息を立てている。
「なんだ・・・こいつの人騒がせな性格は変わっていないな。去年までうちの部署にいたキー坊じゃないか・・・」ユミコの表情が急に穏やかになった・・・
「あら、確かに貴方の部下だった娘ね。そう言えば貴方の事を課長って呼んでいたよ」
「いったい何が起こったのかと思ったぜ」私はとりあえず誤解が解けてホッとした。
「でも、俺に何か用があるのかな?突然現れた理由がわからないけどな」私たち2人は彼女の寝顔を眺めながら、彼女が突然登場した理由を考え続けた。
昨年まで、私は大手の流通会社で会員向け情報のデータ配信をする部署を任されていた。
一般的な業務は部下任せにしていたが、イレギュラーな注文や突発的な案件に関しては、私と女性のアシスタントが担当していた。このアシスタントは本社のシステム部から出向している女性だった。
彼女は逆上すると何をしでかすかわからない凶暴な性格と、几帳面な程の事務処理能力を併せもっていた。
私は彼女をキー坊と呼んで、一緒に仕事をこなしていたわけだ。
 当時は毎晩遅くまでユミコの経営する「デスペラード」で仕事の反省会をやったものだ。
当時は毎晩遅くまでユミコの経営する「デスペラード」で仕事の反省会をやったものだ。
仕事の進め方がいい加減な私と、几帳面な彼女では、目指す結果が同じでもアプローチは違う。
毎晩飲んでいて、よく仕事の話題が尽きなかったと思う。
そして、彼女が突然退職した時、私は頭の中が空っぽになったような気がした事を覚えている・・・
もっとも、彼女は私の友人の会社に転職したのだから、退職の原因は私にあるわけだ。
ジャック・ダニエルズのシャープでサラッとした味覚が私を包んでいる。
同じバーボンでもワイルド・ターキーとはまったく違った味わいが味覚をくすぐり始めていた。
その時、唐突に彼女は目覚め「あら課長こんばんは」と驚いたような声を上げた。
「こら〜!こんばんはも何もあったもんじゃないだろう?お前ここに何しに来たんだよ?」
「実はね、秋山さんに聞いたら、相変わらず課長はこの界隈で飲んだくれているって教えてくれたの」
「秋山の野郎・・・勝手に俺の事を喋りやがって」
秋山は私の友人で昨年Webサーチの会社を数人で立ち上げたばかりだ。
 「私、ここにたどり着くまでに2軒も回り道して飲んじゃったよ〜」彼女はクスッと笑うと私の顔を上目使いで見た。
「私、ここにたどり着くまでに2軒も回り道して飲んじゃったよ〜」彼女はクスッと笑うと私の顔を上目使いで見た。
「実は、今夜ここを訪ねてきた理由なんだけど、秋山さんには無断で課長にメール配信システムの営業をかけにきたんですよ」
「はあ?お前・・・それって本気?」
確かに私の部署は慢性的に人材不足だし、アウトソーシングも考えないわけではないけれど、それにしても・・・
「うちの配信システムは社長が自ら組んだだけあって、なかなかすばらしい出来ですよ」
「導入は私が責任をもってやりますから」
秋山は優秀な営業部員を雇ったものだ(笑)
彼女が秋山の会社に転職するきっかけは、私の会社に秋山が突然訪ねて来た時の会話が発端だった。
秋山は私の運営しているデータ配信システムの不備を厳しく指摘した。その場にいた彼女は凍りついたようになって、秋山の説明を黙って聞いていた。
秋山は単に自分たちが立ち上げたWebサーチの会社の紹介に来ただけだった。ただ、元々SE上がりなだけに、脆弱な我が社のシステムが気になったのだろう。
余計な事を言ってしまったねという顔をして秋山は帰っていった。
秋山が帰った後に、キー坊が呆然としている姿が気になり、私はどうした?と声を掛けた。
彼女は泣き出しそうな顔をしながら「このシステムは私が組んだのです」と呟いた。
 「まあ、秋山の事だから、自分が言い出した事に責任を持ちたかったんだろうな、そして君の考えも一緒なんだろう?」
「まあ、秋山の事だから、自分が言い出した事に責任を持ちたかったんだろうな、そして君の考えも一緒なんだろう?」
「システム導入の件は明日にでも稟議書を切るから、明日から作業を進めてほしい」
「え〜課長!本当ですか?」彼女の声が店内に弾んだ。
「明日にでも見積をメールで送っておいてくれ、それと今夜は遅いから私が送っていくよ」
チラッとユミコが私を見て薄く笑った。
カウンターの上の紙幣はそのままにして、私は立ち上がった。
先に店を出たキー坊の姿を確認した後で「彼女を送って、30分で戻ってくるから軽いつまみを用意してくれ」とユミコに声を掛けて私も店を出た。
ドアが閉まる瞬間に店内の様子がチラッと見えたが、ユミコは幸せそうに微笑みながら冷蔵庫を開けるところだった。
カウンターの上にはジャック・ダニエルズの入ったロックグラスと紙幣が残されている。
表通りではキー坊がタクシーに向けて子供のように両手を振っていた。